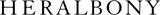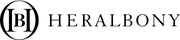Table of Contents
01
FY25の目標
02
事業部戦略変更に伴う
期中の目標見直し
03
FY25の再設定目標
04
目標に対する定量的な結果
05
今期の定性的な振り返り
06
今期の象徴的な取り組み
責任あるものづくり 実践レポート vol.1
Responsible Production
Report vol.1
Table of Contents
HERALBONY(ヘラルボニー)の
責任あるものづくり宣言は、
2024年6月ロゴ変更に伴うリブランディングタイミングに合わせて発表しました。
ヘラルボニーは今後10年、20年と
成長していく過程で、
自社製品のものづくりにおいてネガティブな環境を生み出す加担をしない。
そんな想いから生まれた宣言です。
ヘラルボニーにおいてプロダクトは、
単なるファッションアイテムではなく、
社会に思想・メッセージを届ける存在です。
そのものづくりの過程で、メーカーや自然環境に負担を押し付けるようなことはしたくない。
知らぬ間に誰かの足を踏むような選択を
出来る限りしない。
そんな想いがあります。
この1年は、宣言に掲げた方針や目標を
現場で挑戦するためのスタートの年となりました。
本レポートでは、その1年間の歩みを振り返り、
私たちが掲げた「責任あるものづくり」の方針に対して、
どのようにアクションし、
何を学んだのかをご報告します。
contents
01
FY25の目標
1.
長く寄り添えるクオリティで
長く寄り添えるクオリティで
製品を提供
縫製精度、生地の品質、プリント技術。日常を共にする道具として、クオリティにこだわり、長く寄り添えるたくましさを持った製品作りを大切に。
2.
過度な偏りのない
過度な偏りのない
関係構築で
適量生産へ
大量生産によるコストダウンより、資源が無駄にならない適正な量を生産する。 「適正な量」は、私たちにとっての適正さだけでなく、メーカーにとっての適正さを理解し、話し合いを通して継続的にお取引ができる協力関係をつくる。
3.
生産過程のうち1つ以上工場見学した商品が全体の60%以上
私たちの製品を、どういった方がどのような環境で作っているのか。直接見て、知って、学んでいく。メーカーの工場見学を60%以上行うという目標を掲げ、メーカーとの一歩進んだ協業へと繋げる。
4.
最終製造80%、加工50%、原料30%のトレーサビリティを担保することを目指す
生産工程の段階ごとに、それぞれに具体的な目標を設定して生産背景を把握する。最終製造(縫製などものづくりの最終工程)80%、加工(生地を織ったり染めたりする工程)を50%、原料(コットンやウールなど素材の農場などから糸になるまで)30%という目標に向けて、生産背景を可能な限り追い求める。
5.
自然環境に負荷の低い素材の
自然環境に負荷の低い素材の
使用割合を50%以上へ
限られた資源を使ってものづくりをしていく上で、できる限り温室効果ガスの排出や水や土壌の汚染が少ない農法やリサイクルの素材を積極的に選択します。
contents
02
事業部戦略変更に伴う
期中の
目標見直し
ブランドへの反響が予想を上回るなかで、アップデートし、商品ラインナップの拡充へと舵を切りました。
ブランドの広がりとともに、商品企画や開発のスピードも自然と高まりました。少人数で生産基盤やサイクルがまだ確立されていない状況で、素材選びやサプライチェーン構築にかけられる時間は、これまでより短くなってきました。こうした事業の成長拡大の中で、期初に掲げた「責任あるものづくり」の目標と現実とのあいだに、少しずつギャップが生まれました。
ブランドの広がりとともに、商品企画や開発のスピードも自然と高まりました。少人数で生産基盤やサイクルがまだ確立されていない状況で、素材選びやサプライチェーン構築にかけられる時間は、これまでより短くなってきました。こうした事業の成長拡大の中で、期初に掲げた「責任あるものづくり」の目標と現実とのあいだに、少しずつギャップが生まれました。
ブランドの大方針は経済性と社会性共に両立です。プロダクトチームでは、この目標と現実のギャップと真摯に向き合いながら、「責任あるものづくり宣言」が理想論として一人歩きすることのないよう、実践のなかで見えてきた「できること」と「難しいこと」をあらためて見つめ直しました。チームでディスカッションを重ねて、現状の体制・スピード感の中でも継続的に取り組めること、そして現状を正しく把握した上で残り半年間を通して挑戦できる最大限の目標をチーム全体で議論を重ねて再設定しました。
contents
03
FY25の
再設定目標
- 1. 全プロダクトのメイン素材のうち、20%が自社選定基準リストに該当
- 2. 全プロダクトの製造先のうち、FY25に下期3件訪問(2ヶ月に1件訪問)
- 3. 全プロダクトの製造工程のうち、最終工程を50%、加工30%、生地20%のトレーサビリティを担保する
※トレーサビリティ担保とは、工場を把握している状態とヘラルボニーでは定義
生地の把握とは、原料から素材にする織り等の工程を実施した工場を把握していると定義
生地の把握とは、原料から素材にする織り等の工程を実施した工場を把握していると定義
再設定した目標に対して継続的に実践できるようにアイテム単位でメイン素材とトレーサビリティを把握するリストを作成し、
チームで定期的に振り返る枠組みを構築しました。合わせてメイン素材選定の方針を決めました。
チームで定期的に振り返る枠組みを構築しました。合わせてメイン素材選定の方針を決めました。
第1優先
トレーサビリティが担保され、基準リストに適合する素材の中から予算・スケジュール・クオリティの条件に合った最適な生地を模索
第2優先
マッチしなければ予算とスケジュール、クオリティで選定し、手に取り愛着持って使っていただける商品作りへ
contents
04
目標に対する
定量的な結果
1.
全プロダクトのメイン素材のうち、20%が自社選定基準リストにマッチ
結果
担保アイテム数 11
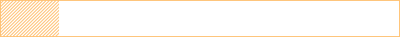
16.18% / 100%(全68アイテム)
現在のブランド力と企画・生産のリードタイムの状況では、素材の自社オリジナル製造は難しいです。基本的にはメーカーの在庫から仕入れる形となるため、原料から生地になるまでのフローを詳細に把握することは容易ではありません。そのため、素材選定にあたっては認証を基準とする方針を採用し、納得感のある選定につながるよう高い基準を設定しています。今期はオーガニックコットンやリサイクルポリエステル素材を使用したものの、認証基準を満たしていないケースが見られました。
一方で、メーカーとの関係性も深化し、自社企画に応じた認証取得予定の生地のご紹介や、生地製造先の情報共有いただける機会も増えています。
今後は、企画・生産のリードタイムを十分に確保し、素材選定や生地生産の時間を拡充することで、選択肢を増やせる体制を整えていきます。
また、定番製品については、選定基準をクリアした生地へアップデートするフローの展開も予定しています。
一方で、メーカーとの関係性も深化し、自社企画に応じた認証取得予定の生地のご紹介や、生地製造先の情報共有いただける機会も増えています。
今後は、企画・生産のリードタイムを十分に確保し、素材選定や生地生産の時間を拡充することで、選択肢を増やせる体制を整えていきます。
また、定番製品については、選定基準をクリアした生地へアップデートするフローの展開も予定しています。
2.
全プロダクトの製造先のうち、下期3件訪問(2ヶ月に1回訪問)
結果
目標訪問 3件中 4件達成
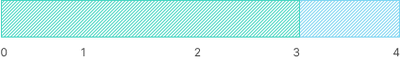
タイトな商品企画・製造の進行状況により、製造先を訪問する機会を確保するのが難しい状況でしたが、今期は、下期に発表したブラウス・シャツ・スカート・ワンピースの最終製造を担当していただいている岐阜のレスカリエさま、ハンカチの最終製造を担うカヤマさまを見学しました。また、実際にアートを表現する工程を見学・撮影しに革小物のメーカーと、浴衣を製造いただいた岩手の京屋染物店も訪問しました。
製造現場を直接拝見し、自社製品を作ってくださっている方々の様子を知ることは、商品に対する想いをより一層深めるとともに、お客さまへお届けする際の自信にもつながりました。
また、工場との信頼関係の築くことで、商品のクオリティ向上にも寄与しています。
来期は、期初から定期的な訪問スケジュールを立てて実施し、継続的な再訪問を通じて、製造現場との対話を深めながら、丁寧な関係を育んでいきたいと考えています。
製造現場を直接拝見し、自社製品を作ってくださっている方々の様子を知ることは、商品に対する想いをより一層深めるとともに、お客さまへお届けする際の自信にもつながりました。
また、工場との信頼関係の築くことで、商品のクオリティ向上にも寄与しています。
来期は、期初から定期的な訪問スケジュールを立てて実施し、継続的な再訪問を通じて、製造現場との対話を深めながら、丁寧な関係を育んでいきたいと考えています。
3.
全プロダクトの製造工程のうち、最終製造を50%、加工30%、生地20%のトレーサビリティを担保する
結果 : 生地
担保アイテム数 14
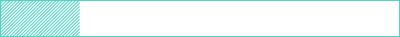
20.59% /100%(全68アイテム)
事業の特性上、アートの表現が主軸であるため、ネクタイのジャガード織りのように、織りそのものがアート表現に直結する場合は、製造背景を比較的把握しやすいです。
一方で、アートをプリントで表現する際の“土台”となる生地については、オリジナルでの製造が費用・時間の観点から難しく、メーカーのストック生地を使用することが多いため、その背景まで把握するのは容易ではありません。
今後は、メーカーと引き続き協力関係を深め、背景情報の可視化に向けて丁寧なコミュニケーションを重ねていきます。現在、1アイテムあたりの製造ロットが小さいためオリジナルの生地をアイテム単位で製造することは難しい状況です。しかし、生地の製造先生地の製造先とも関係性を築きながら、使用する素材の背景がより担保できる体制と環境づくりを進めていく方針です。
一方で、アートをプリントで表現する際の“土台”となる生地については、オリジナルでの製造が費用・時間の観点から難しく、メーカーのストック生地を使用することが多いため、その背景まで把握するのは容易ではありません。
今後は、メーカーと引き続き協力関係を深め、背景情報の可視化に向けて丁寧なコミュニケーションを重ねていきます。現在、1アイテムあたりの製造ロットが小さいためオリジナルの生地をアイテム単位で製造することは難しい状況です。しかし、生地の製造先生地の製造先とも関係性を築きながら、使用する素材の背景がより担保できる体制と環境づくりを進めていく方針です。
結果 : 加工
担保アイテム数 43
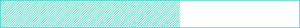
63.24% /100%(全68アイテム)
主な加工工程は、生地へのプリントです。アイテム数が増加している中でも、プリントを担う工場は厳選しており、加工背景の担保率は高い水準を維持しています。また、一部のアイテムについては、社内メンバーが中心となってサプライチェーンを構築しているため、背景の把握がしやすい体制も整っています。アートの表現はブランドにとって大切な要素なので、厳選した工場との継続的な関係を通じて、ものづくりの透明性と信頼性を高めていきます。
結果 : 最終製造
担保アイテム数 64
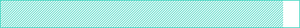
94.12% /100%(全68アイテム)
最終製造先についても数を絞っているため、製造背景の担保率は高い状況にあります。また、製造の大半が国内で行われていることから、工程の把握もしやすい体制となっています。
今後、ブランドが5倍、10倍と急速に成長していくことを見据え、キャパシティとクオリティの双方が見合う最終製造先を、引き続き構築していく予定です。
今後、ブランドが5倍、10倍と急速に成長していくことを見据え、キャパシティとクオリティの双方が見合う最終製造先を、引き続き構築していく予定です。
今期の定性的な
振り返り
contents
05

contents
05
成長した先で堂々と社会の人権意識を
成長した先で堂々と
社会の人権意識を
一歩前進できたと言えるよう、
実践できる範囲を模索し、
継続的にものをつくる責任を果たす。
期初に掲げた志と、それを実際に成し遂げることの難しさを痛感した1年でした。ヘラルボニーは、異彩を放つ作家の才能を社会に届け、それを通して障害のイメージを変容することが事業ミッションです。どんなものにでも載せることができるアートだからこそ、あえて条件を設けてプロダクトを企画することは、ものづくりの難易度を上げる選択です。それでも、私たちは諦めませんでした。プロダクトチームで幾度も話し合いを重ね、「今できること」に立ち返りながら目標を再設定し、この一年、試行錯誤を止めることなく走り抜きました。小さな一歩に見えても、それを積み上げた事実こそが、私たちにとっての確かな成果です。人へのリスペクトを大切にするヘラルボニーらしく、まずは可能な範囲で製造先を丁寧に把握し、実際に足を運んで工場を見学し、顔を合わせる。そのプロセスによって、私たち自身が商品に対してさらに強い想いを持ち、丁寧にお届けしたいという気持ちが自然と高まっていく、そんな好循環が生まれました。完璧ではないけれど、この姿勢がチームに根づき、続けられる体制が少しずつ育ちつつあります。
来期以降、ブランドはさらに加速度的に成長していくことを描いています。まずは今期に構築した取り組みを継続するとともに、今後定番化していくアイテムの素材についても、選定基準に照らし合わせ、アップデートしていく予定です。
製造背景を把握するなど、サプライチェーンに条件を設けることは、時間も、コストも、エネルギーもかかります。そのコストが製品価格に反映されたとき、理由をご理解いただいていたとしても、「高い」と感じられる場面があることも、私たちは十分に認識しています。短期間で10倍、100倍の成長を目指すブランドにとって、価格が売上に与える影響は小さくありません。それでも、成長した先で堂々と社会の人権意識を一歩前進できたと言えるよう、多くの方にご協力いただく自社製品において実践できる範囲を継続的に模索し、ものをつくる責任を果たしていくことに挑戦していきます。
製造背景を把握するなど、サプライチェーンに条件を設けることは、時間も、コストも、エネルギーもかかります。そのコストが製品価格に反映されたとき、理由をご理解いただいていたとしても、「高い」と感じられる場面があることも、私たちは十分に認識しています。短期間で10倍、100倍の成長を目指すブランドにとって、価格が売上に与える影響は小さくありません。それでも、成長した先で堂々と社会の人権意識を一歩前進できたと言えるよう、多くの方にご協力いただく自社製品において実践できる範囲を継続的に模索し、ものをつくる責任を果たしていくことに挑戦していきます。
contents
06
今期の象徴的な
取り組み


1.
販売数上位製品の素材アップデート
ブランド内で最も販売数の多いハンカチを、オーガニックコットン素材に切り替え。また、人気のサブバッグについても、期中にGRS認証を取得したリサイクルポリエステル素材へと移行。
2.
トレーサビリティを基準とした製品展開
原料段階からのサプライチェーン全体のトレーサビリティを担保した「ISAIシャツ」「ISAI BAG」を開発・展開。
3.
製造現場の視察から始まった素材選定
素材となるシルク養蚕の現場訪問からサプライチェーンを構築したシルクサテン素材のスカーフを開発・展開。