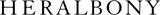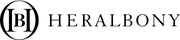盛岡の夏に、記憶をまとう
企画概要
さんさ踊りと人々の物語を、浴衣で写す

ヘラルボニーが手がけたオリジナル浴衣をまとい、盛岡の街にゆかりある方々にご登場いただくスナップ企画を実施。
そばを運ぶ人、コーヒーを淹れる人、金属を打つ人、食卓を営む人——。
それぞれの場所で日常を支え、地域とともに時を重ねてきた この街に生きる人々が語ってくれたのは、さんさ踊りの音に誘われるように浮かび上がる「個人の記憶」と「家族の物語」でした。
娘の笑顔、祖母の花笠、通りすがりのひと言、夫婦で見上げたパレード。
伝統は、こうしたひとつひとつの暮らしの中に息づいています。
浴衣をまとい、その想いを語る姿は、どれも凛として、美しい。
盛岡という場所と、そこに生きる人々の物語を、そっと写し取った企画です。
01
さとう 理香|東家
「笑顔」がつなぐ、そばと、さんさ踊りと、母娘の時間。
盛岡の老舗わんこそば店「東家」で、給仕のかけ声とともにそばが舞うように差し出される光景は、この街の風物詩のひとつ。
そんな東家で、40年勤め続けてきたのが、さとう理香さん。10代からこの店一筋、今では店長として、日々変わらぬ笑顔でお客様を迎えています。
そんな東家で、40年勤め続けてきたのが、さとう理香さん。10代からこの店一筋、今では店長として、日々変わらぬ笑顔でお客様を迎えています。
東北を代表するお祭りに“娘が出る”ということ

「さんさ踊りを初めて知ったのは10代の頃。“東北四大祭り”に名を連ねるような、大きなお祭りだと知りました。密かに、ねぶた祭りに勝ってほしいなって思ってるんです(笑)」
そう語るさとうさんですが、今はさんさ踊りに特別な想いがあります。
「娘がさんさ踊りにハマって、今ではパレードで踊っているんです。実は、娘も同じく東家で一緒に働いていて。お店でも一生懸命にお客様と向き合い、夏になると外では踊りで自分を表現していて。そんな娘の姿を見るのが、私は本当に嬉しいんです。どちらの姿も、そのままの彼女らしくて、あの瞬間が、いちばん幸せですね。」
「娘がさんさ踊りにハマって、今ではパレードで踊っているんです。実は、娘も同じく東家で一緒に働いていて。お店でも一生懸命にお客様と向き合い、夏になると外では踊りで自分を表現していて。そんな娘の姿を見るのが、私は本当に嬉しいんです。どちらの姿も、そのままの彼女らしくて、あの瞬間が、いちばん幸せですね。」
お祭りの日も、そばの香りと笑顔を

さんさ踊りの期間中、街はにぎわいを増しますが、東家の空気は少しゆったりと。
「観光のお客様は増えるけど、お祭りを観に行く方が多いので、実は店内は落ち着いているんですよ。私たちも、そっと抜け出して見に行くこともあります。」 お祭りの熱と、そばの湯気がすれ違うような、盛岡らしい夏の日常です。
40年という時間、東家という場所、そしてさんさ踊りとともにあった家族の物語。 さとうさんのやわらかな笑顔に、人生の積み重ねがそっとにじんでいました。
「観光のお客様は増えるけど、お祭りを観に行く方が多いので、実は店内は落ち着いているんですよ。私たちも、そっと抜け出して見に行くこともあります。」 お祭りの熱と、そばの湯気がすれ違うような、盛岡らしい夏の日常です。
40年という時間、東家という場所、そしてさんさ踊りとともにあった家族の物語。 さとうさんのやわらかな笑顔に、人生の積み重ねがそっとにじんでいました。
02
長澤 ゆかり|Nagasawa COFFEE
コーヒーと、花笠と、祖母の記憶。
盛岡・上田に構える「Nagasawa COFFEE」は、生豆の仕入れから焙煎、抽出、提供までを一貫して行うロースターカフェ。 ヘラルボニーの旗艦店 HERALBONY ISAI PARKでは、Nagasawa COFFEEが焙煎したヘラルボニーオリジナルブレンドを使用しています。 お話を伺ったのは、Nagasawa COFFEE 長澤 ゆかりさん。日々の静かな営みと、盛岡の夏の記憶について語ってくださいました。
花笠をかぶった、祖母の後ろ姿

「さんさ踊りといえば、祖母の姿が浮かびます。花笠をかぶって、さっと家を出ていく姿を今でも覚えています。昨年亡くなったんですが、仏壇には祖母の花笠が置いてあるんです。」そう静かに語ってくれたゆかりさんにとって、さんさ踊りは「懐かしい人の記憶」と結びついているもの。だからこそ、その熱量と一体感が、今ではより鮮やかに感じられるといいます。
お祭りと、日常と。

「踊りひとつで、人と人、人と地域の絆が生まれる。それってすごいことですよね。」
そう話しながらも、Nagasawa COFFEEの営業スタイルはさんさ踊り期間中も変わりません。
「うちは“日常に寄り添うお店”なので、さんさの影響はあまりないですね。お祭りと日常、それぞれの時間があっていいと思います。」
コーヒーの湯気の向こうにある、街へのまなざし。 いつもの一杯のなかにも、花笠の記憶と、静かな熱がそっと宿っていました。
コーヒーの湯気の向こうにある、街へのまなざし。 いつもの一杯のなかにも、花笠の記憶と、静かな熱がそっと宿っていました。
03
横山 慶・歩美|RHINO
さんさ踊りの音で、夏が来る。盛岡の街とRHINOの日常。
盛岡の人気店「RHINO」を営む横山慶さん・歩美さんご夫妻。食と暮らしを丁寧に見つめるおふたりにとって、盛岡の夏を象徴する さんさ踊りは、どんな存在なのでしょうか。
“初めて見たとき、涙が出たんです”

歩美さんは新潟出身。初めてさんさ踊りを見たのは、盛岡に越してきたあとだったといいます。
「夫に連れて行ってもらって見たんですが、すごくて…涙が出ました。あれだけ大勢が一緒に踊るお祭りって、なかなかないですよね。」
「なかでも学生さんたちの踊りが好きで。勢いがあって、一生懸命さが伝わってきます。若い世代がしっかり残していこうとしているのが、いいなって思います。」
小学生の頃から、地元の「黒川さんさ」

「僕の地元は、今は盛岡市に合併された旧・都南村。小学生の頃、地域に伝わる“黒川さんさ”を初めて踊りました。地元の有志で1968年に復活した、伝統のさんさ踊りです。」
そう話す慶さん。今は“見る派”だと笑います。
「子どもの頃は自分が踊っていたけど、今は見るのが楽しい。さんさ踊りが近づくと、街のあちこちから笛や太鼓の音が聞こえてきて、“あ、夏が来たな”って感じるんです。」
盛岡の街のなかで、さんさ踊りの音とRHINOの日常が交差する夏。さりげなく美しいものを選ぶ人たちの時間が、この店から、また静かに広がっていきます。
盛岡の街のなかで、さんさ踊りの音とRHINOの日常が交差する夏。さりげなく美しいものを選ぶ人たちの時間が、この店から、また静かに広がっていきます。
04
鈴木盛久|鈴木盛久工房 十六代
“さんさ”と“鋳金”。盛岡の街で息づく、静かな伝統と個性。
1972年、盛岡に生まれ、東京藝術大学美術学部工芸科で鋳金を学んだ鈴木盛久さん。2008年より家業である鋳金工芸の世界へと本格的に足を踏み入れ、2022年には「第16代 鈴木盛久」を襲名。伝統を受け継ぎながらも、新しい風を柔らかく取り込む姿は、この街の“今”そのものです。そんな鈴木さんに、夏の風物詩 さんさ踊りについて、お話を伺いました。
“さんさ、見るのは好きなんです”

「僕自身は、パレードに出たことはないんです。でも、盛岡市内の小学生は学校で さんさ踊りを習って、運動会で踊るんですよ。」
そう語る鈴木さん。子どもの頃から身近にある さんさ踊りですが、踊ることよりも、どちらかというと“見る派”なのだとか。
「若い頃はさんさ踊りにも行くけど、どちらかというと屋台の方が楽しみだった。でも、年を重ねるにつれて、踊りの種類や伝統さんさの素晴らしさなどが理解できるようになってきて。今は純粋に、踊りを眺めるのが楽しいですね。」
さんさ踊り期間中の工房や商店街の様子を尋ねると、「特に変わらないよ」と、にこやかに笑います。きっとその変わらなさが、日々を支えているのかもしれません。
ヘラルボニーの浴衣と、盛岡の日常。

ヘラルボニーのオリジナル浴衣の装いにひときわ目を引いたのが、トレードマークのベレー帽。
「帽子が好きで以前はよくハットやキャップを被っていたんですが、最近は専らベレー帽でトレードマークのようになっています(笑)」
通りがかる地元の方からは「まぁ、素敵ね」と声がかかるほど。盛岡の街で、鈴木さんはすっかり“盛久さん”として愛されている存在です。
工房に流れる静けさと、商店街のにぎわい。そのどちらにも自然体で立つ“盛久さん”の姿に、伝統とは“続いていくこと”の積み重ねなのだと教えられるようでした。
工房に流れる静けさと、商店街のにぎわい。そのどちらにも自然体で立つ“盛久さん”の姿に、伝統とは“続いていくこと”の積み重ねなのだと教えられるようでした。