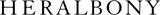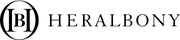装うことは、意思表明になる。俳優・星野真里が語る、“知る”ことから始まった装いと価値観の変化

人生の節目といった特別なシーンを迎えるとき、私たちはいつもより少しだけ立ち止まり、装いを選ぶ。その選択は、場にふさわしいかどうかという判断であると同時に、「今の自分」をどう在らせたいかという、静かな意思表明でもあります。
俳優として長く活動しながら、一人の母として日々を重ねてきた星野真里さん。娘さんとの時間を通して、「当たり前」や「普通」といった価値観は、少しずつ、しかし確かに変化してきたといいます。2024年9月には長女・ふうかさんが先天性ミオパチーであることを公表。「同じような環境にある人に情報を届けたい」との思いから始めたInstagramでは、今、多くの人がその言葉に耳を傾けています。
娘さんとの日々を通じて育まれてきた価値観、装いに対する考え方、そして人生の節目を迎えることの意味。今回は、星野さんにヘラルボニーのスカーフアタッチメントワンピースをまとっていただき、「オケージョン(特別な日)」をテーマに、お話を伺いました。
表現としてのアートに惹かれて──星野さんとヘラルボニーの出会い

—まずはじめに、星野さんがヘラルボニーに出会ったきっかけを教えてください。
星野真里さん(以下、星野):きっかけは、朝の情報番組を担当していたときでした。TBSさんとのコラボで制作されていたトートバッグがとても可愛くて、気になって調べたんです。そこで、障害のある方のアートだと知りました。作品そのものの力に惹かれたのはもちろんですが、福祉やボランティアという枠にとどまらず、きちんと商品として、ビジネスとして成立させている点がとても素晴らしいなと感じました。オンラインショップもよく拝見していますが、本当に素敵なアイテムばかりですよね。
—ありがとうございます。ヘラルボニーの商品について、どのような印象をお持ちですか?
星野:素晴らしいアートを生み出す作家さんたちを、「本物のアーティスト」としてまっすぐ世に届けている印象があります。その姿勢が、とても誠実だなと感じました。決して安いものではありませんが、それでも「大切な人に手渡したい」と思える魅力がある。そうした点も含めて、すごく素敵だなと思っています。
装いは、日常と非日常をつないでくれるもの
—普段、人に会う日と、ご自身やご家族だけで過ごす日とで、気持ちが切り替わる感覚はありますか?
星野:あると思います。でも、毎回はっきり意識しているわけではなくて。朝になって予定を確認して、「今日は何もない日だ」と分かると、そのままリラックスモードで一日が進んでいきます。
一方で、「今日は仕事がある」と分かると、何時から俳優としての自分が始まるのか、自然と心の中で区切りをつけている気がします。それまでは家で過ごすいつもの私でいて、そこから外に出る準備の時間に入る。装いも、その切り替えのひとつなんだと思います。
—入学式のような特別な日を迎えるにあたって、装いについて意識することはありますか?
星野:いわゆるオケージョンって、当日だけじゃなくて、もっと前から始まっている気がします。その準備の時間も含めて、すごく楽しいんですよね。
どんな雰囲気で、どんな私でいたいか。子どもと一緒の行事であれば、娘にどんな母として見てもらいたいか。そんなことを想像しながら装いを選んでいるんだと思います。振り返ると、ずっとそうしてきた気がしますね。

旅行って特別な時間ですし、写真もいつもよりたくさん撮る。だから、ただ着心地がいいだけじゃなくて、あとから振り返ったときに「この日の私を覚えていたいな」と思える装いにしたい、という気持ちもありました。娘や主人と一緒に写真を見返したとき、そのときの私が、ちゃんと記憶として残っていたらいいなと思いながら選んでいた気がします。
—娘さんから、母親としてどう見られたいかを気にされているのが印象的です。
星野:私の母は、TPOをとても大切にする人でした。子どもの頃は、それが少し面倒に感じることもあったんですが、今思うと、その感覚がちゃんと自分の中に残っているんですよね。
人の視線を意識しすぎる必要はないと思いますが、どんな場所にいても堂々としていられること、自分が心地よく過ごすための装い、という考え方もあると思うんです。
普段はスウェットで過ごす日もあるけれど、人と会うときには、こんな一面もあるんだよ、という可能性として。装いって、遊べるものでもあるし、自分を伝えるひとつの手段でもある。そんなことを、無意識のうちに娘に見せているのかもしれないですね。
—そうした星野さんの姿を見たときの、娘さんの反応はいかがですか?
星野:「今日どうしたの?」とか、「いつもと違うね」とか。アクセサリーをつけていると、「そんなの持ってたの? 今度貸して」なんて言われることもあります(笑)。母としてだけでなく、一人の女性として見てくれているんだなと感じられて、嬉しいですね。
年齢とともに変わっていった、装いとの距離感
—ご自身の年齢や、お子さんの成長につれて、装いに対する心境の変化はありましたか?
星野:正直に言うと、いわゆる「こうあるべき」という考え方には、ずっと抗いたい気持ちがありました。年齢を重ねたからといって、足を出したいときは出してもいいし、母であっても女性であっても、たまにはこういう格好をしてもいいよね、と思うんです。一方で、娘に対しては、「この場ではこういう装いが一般的だよ」と伝えたい自分もいる。その二つのあいだを、ずっと行き来している感覚はありますね。

ひとりで行動するときは、思うままに装う。でも、娘と一緒に場に立つときには、自然と“母としての姿”を意識します。何かを伝える立場である以上、自分が言っていることを自分で崩してしまうと、お手本にならない気がして。「こういう場では、こんな装いもあるよ」と、母としてひとつの参考を示すことは、意識しているのかもしれません。
でも今は、それもそれでいいけれど、流れに身を任せるのも悪くない、と思えるようになってきました。「正解」を探すより、そのときの自分が選んだものを信じてみる。今のほうが、ずっと楽ですね。
「当たり前」を問い直すきっかけになった、娘との時間
—そうした柔軟な考え方にたどり着いた背景には、何があったのでしょうか?
星野:やっぱり、娘と過ごす時間が大きいと思います。私が抗っていたのは、自分の中で勝手につくり上げていた「普通」や「当たり前」だったんですよね。そうならなきゃいけない、でもそうなりたくない。そのあいだで、ずっと揺れていた気がします。
娘は、肢体に不自由があって、成長の仕方もいわゆる一般的な成長曲線とは違います。その姿を日々見ているうちに、「普通って何だろう?」「当たり前って、誰の基準なんだろう?」と考えるようになりました。
今まで当たり前だと思っていたことを、少し手放してみても、実は何も困らない。そう気づいたときに、無意識のうちに引いていた境界線が、ふっと緩んだような感覚がありました。だから今は、どこにいても、もう少し自由でいていいのかな、と思えるようになりました。

—装いにも、そうした変化は表れていますか?
星野:つながっていると思います。娘は車椅子で生活しているので、フードが引っかかったり、丈が短いと動きづらかったり、どうしても難しい装いがあります。そうした制限を身近で感じているからこそ、逆に考えるようになりました。「今の私は、どんな制限を自分に課しているんだろう?」って。
以前は、人前に出る仕事ということもあって、「どう見られるか」を前提に装いを選んでいた時期もありました。「着たい服と、似合う服は違う」と言われて、それを基準に選んでいたこともあります。
でも今は、着たときの着心地や、鏡に映った自分の感覚、それから、娘からどう見えているか。そういう半径一メートルくらいの、身近な心地よさを大切にしています。周りにどう映るかよりも、まず自分が自然でいられるかどうか。それが、今の装いの基準ですね。
アートを身にまとうことは、その先にいる人に想いを馳せること
この日、星野さんが選んだのは、滋賀県のやまなみ工房に在籍する作家・中尾涼さんの作品を用いたスカーフ。数字をモチーフにした作風で、多くの作品に「14」までの数字が描かれているのが特徴です。幼い頃、おばあさまとドライブをした際に聴いていたCDのトラックが14番まであったことが、その着想のものになっているそう。

シルクスカーフ「タイトル不明」
スカーフアタッチメントワンピース
—スカーフアタッチメントワンピースを着た感想はいかがですか?
星野:どこか距離を置いて鑑賞するものとして捉えているアートが、急にすごく身近になる感覚があって。遠くにあるものだと思っていた存在が、自分の肌の上で形を変えて存在している。その感覚が、とても新鮮に感じました。
ブラックのワンピースに合わせるスカーフは、巻き方や色の出し方で印象が大きく変わりますよね。顔まわりにまとめてもいいし、腰に巻いてもいい。ひとつのアイテムなのに、楽しみ方がいくつもあるなと感じました。

—アートであるスカーフを身にまとって、どんなことを感じられましたか?
星野:強く感じたのは、「ものの先には人がいる」ということですね。アートは、作り手が「これが私たちの作品です」と覚悟をもって世に差し出すもの。それを日常の中で身にまとい、生活の一部として楽しめるというのは、とても贅沢なことだと思いました。
中尾さんのエピソードを聞いて、その感覚はいっそう深まりました。たとえもうこの世にいない方の記憶であっても、作品を通して確かに今につながっている。アートには、時間や想いを超えて、人と人を結ぶ力があるのだと感じました。
娘さんとともに考える、これからのオケージョン
—これから娘さんと一緒に迎えるオケージョンでは、どんな所が楽しみですか?
星野:今までの大きなオケージョンでいうと、入学式が一番近い出来事でしたが、あの頃はまだ「一緒に相談する」という段階ではなかったなと思います。でも、これから迎える卒業式や入学式では、一緒に考えたりできるんだろうなと想像すると、ワクワクしますね。装いをきっかけに、またひとつコミュニケーションが生まれて、その時々のお互いの気持ちを知っていく。そんな時間になったら素敵だなと思いますし、今後がすごく楽しみです。

正解よりも、「決める」という行為を大切にしたい
—装いの選び方の変化は、ご自身の生き方とも重なりますか?
星野:重なりますね。そもそも、正解ってそんなに簡単にあるものじゃないと思うんです。たとえば今回の本づくりも、「正解」という道筋が最初からあったわけではなくて、その都度話し合いながら、「ここまでを今の完成にしよう」と決めてきました。その“決める”という行為自体が、とても大切だったなと感じています。装いも同じで、迷いながらでも「今日はこれ」と一度決めて外に出ることが大切だと思っています。正解を探し続けるより、自分で選んでみること。もし何か言われて「確かにそうかも」と思えたら、そのときに変えればいい。何も決めずに隠れてしまうより、一度ちゃんと選んで立ってみるほうが、ずっと健やかだなと感じています。
私にとって装うことは、「今の私はこうです」と自分に示す、ささやかな意思表明ですね。

『さいごにきみと笑うのだ ~ふうかと紡ぐふつうの日々とふつうじゃない幸せ~』(星野真里著/小学館)。「先天性ミオパチー」という国指定難病を患い電動車椅子で生活している長女・ふうかさん。難病と共生する現実の中にある、ちょっと大変だけど少し楽しいエピソードを、母・真里さんの視点で綴るエッセイ。
「知る」ことで、世界の輪郭が変わっていく
—星野さんの価値観や日常の選択が今回の著書『さいごにきみと笑うのだ』にもあらわれていますね。この本を通して、伝えたいことはどんなことでしょうか。
星野:一番伝えたかったのは、「知ること」の大切さです。娘と出会うまでの約40年間、私は障害や福祉、難病について深く考えたことがありませんでした。同じ社会にいながら、どこか自分とは別の世界のこととして捉えていたんです。

でも、知ることで世界の見え方は大きく変わりましたし、結果的に私は生きやすくなりました。だからこそ、この経験を言葉にすることで、誰かが気づくきっかけになったらいいなと思っています。
共生社会も、何か大きな出来事で一気に実現するものではなくて、日常の小さな理解の積み重ねの先にあるものだと思います。特別なメッセージを届けたいというより、私たち家族のごく普通の10年を、そのまま見て欲しい。そこから「違う」と感じる人も、「同じ」と感じる人も、そのどちらもが大切な一歩だと思っています。
まずは少しでも身近に感じてもらうこと。その入り口として、この本があれば嬉しいですね。
星野 真里
Mari Hoshino
1981年7月27日生まれ。埼玉県上福岡市(現・ふじみ野市)出身。 1995年、NHK「春よ、来い」でデビュー。同年TBSテレビ「3年B組金八先生」において坂本乙女役を好演、広く認知される。2005年「さよならみどりちゃん」で映画初主演し、第27回ナント三大陸映画祭主演女優賞を受賞。現在ではドラマ、映画、舞台、CM等女優業の他にコメンテーター、番組司会、エッセイ執筆、ナレーション等、幅広い分野にて足跡を残している。 Instagram:@mari_hoshino.7.27